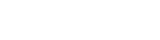『五右衛門風呂』の由来とは?|浴場の小ネタ(86)
出典:photoAC(燃え盛るかまどの熱で湯が温められます)
この記事を書いた人
湯あがり ぽか子
温泉大好き40年のベテラン。「一湯一会」を逃さないために、常に手ぬぐいを持ち歩いています。長年の経験で、お湯を触っただけで大体の泉質がわかる特技を持ちます。温泉好きが高じて、温泉ソムリエ・温泉観光アドバイザーの資格を取得。日本の宝である「温泉文化」を皆さんにお伝えできることが喜びです!
日本の温泉・銭湯で楽しめるお風呂には、『風呂』という言葉の前に別の名前が付くものが多くあり、例えば露天風呂・岩盤風呂・水風呂・電気風呂などが私たちの生活に根付いています。
そのような中で、最近はあまり見なくなったお風呂として『五右衛門風呂』というお風呂があります。かまどの上に鉄釜を置いて湯を焚くスタイルのお風呂であり、一度は写真や映像で見たことがある方も多いのではないでしょうか。
さて、そのお風呂自体に人名が付いている五右衛門風呂ですが、その名前の由来を皆さんはご存じでしょうか?
目次
浴場の小ネタは3択クイズ。正解はどれ?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
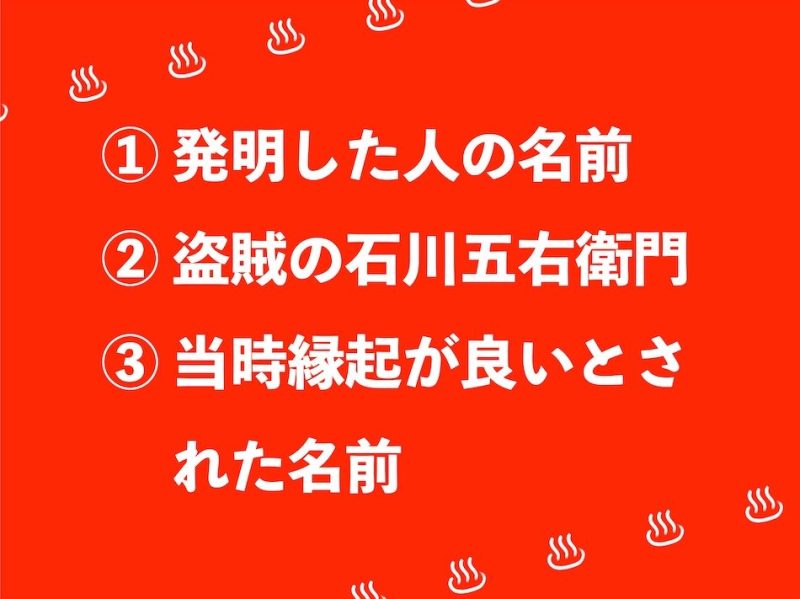
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
浴場の小ネタ「『五右衛門風呂』の由来とは?」の答えはこちら

出典:photoAC(温泉地で見かけたときは、その歴史に想いを馳せてみましょう)
正解は、「 ② 盗賊の石川五右衛門 」でした。
その由来は、安土桃山時代の盗賊・石川五右衛門に対する刑として、豊臣秀吉が鉄釜の熱湯に彼を入れて処刑したことが由来となっています。
実際に五右衛門風呂に入る際は、木製・樹脂の浮き蓋を沈めて入浴するようになっており、火傷をする心配はありません。また、最近では新規に作られた五右衛門風呂を見かけることはほとんどなくなりましたが、現在でも日本国内で唯一五右衛門風呂を作り続けているメーカーもあり、その歴史を今に語り継いでいます。